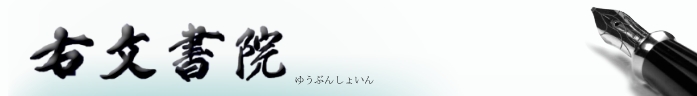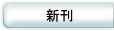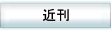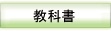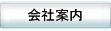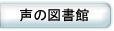徒然草 説話 枕草子(古A311)
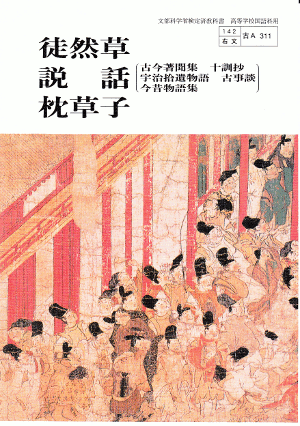
A5判・128ページ 2単位
-
徒然草
- 序段 つれづれなるままに
- [世相奇談]
- 一 公世の二位のせうとに(第四五段)
- 二 仁和寺にある法師(第五二段)
- 三 これも仁和寺の法師(第五三段)
- 四 延世門院(第六二段)
- 五 西大寺の静然上人(第一五二段)
- 六 丹波に出雲といふ所(第二三六段)
- [芸の道]
- 一 亀山殿の御池に(第五一段)
- 二 ある人、弓を射ることを習ふに(第九二段)
- 三 能をつかんとする人(第一五〇段)
- 四 よろづの道の人(第一八七段)
- 五 よき細工は(第二二九段)
- [人生随想]
- 一 家居のつきづきしく(第一〇段)
- 二 神無月のころ(第一一段)
- 三 久しく隔たりて(第五六段)
- 四 今日は、そのことをなさんと(第一八九段)
- 五 達人の人を見る眼は(第一九四段)
- 六 園の別当入道は(第二三一段)
- [四季ともののあはれ]
- 一 折節の移り変はるこそ(第一九段)
- 二 万の事は、月見るにこそ(第二一段)
- 三 雪のおもしろう降りたりし朝(第三一段)
- 四 花はさかりに(第一三七段)
- [無常の相]
- 一 あだし野の露(第七段)
- 二 五月五日、賀茂の競馬を見はべりしに(第四一段)
- 三 大事を思ひたたん人は(第五九段)
- 四 蟻のごとくに集まりて(第七四段)
- 五 つれづれわぶる人は(第七五段)
- 六 世に従はん人は(第一五五段)
- 七 人間の営みあへるわざを見るに(第一六六段)
- 終段 八つになりし年(第二四三段)
-
説話
-
古今著聞集
- 一 いろはの連歌(巻第五)
- 二 能は歌詠み(巻第五)
- 三 刑部卿敦兼と、その北の方(巻第八)
-
十訓抄
- 一 文字一つの返し(第一)
- 二 笛吹きの成方と名器「大丸」(第七)
-
宇治拾遺物語
- 一 きこりの歌(巻三)
- 二 伴大納言応天門を焼く(巻一〇)
- 三 猿沢の池の竜の事(巻一一)
- 『竜』(芥川龍之介)
- 四 夢を買ふ人の事(巻一三)
-
古事談
-
今昔物語集
- 一 受領は倒るる所に土をつかめ(巻二八)
- 二 わが影に恐れをなす男(巻二八)
-
枕草子
- [四季随想]
- 一 春はあけぼの(第一段)
- 二 正月一日は(第三段)
- 三 卯月のつごもり方に(第一一〇段)
- 四 九月ばかり(第一二五段)
- 五 五月ばかりなどに山里にありく(第二〇七段)
- [ものづくし]
- 一 すさまじきもの(第二三段)
- 二 過ぎにしかた恋しきもの(第二八段)
- 三 鳥は(第三九段)
- 四 あてなるもの(第四〇段)
- 五 ありがたきもの(第七二段)
- [宮廷生活]
- 一 上に候ふ御猫は(第七段)
- 二 中納言参りたまひて(第九八段)
- 三 二月つごもりごろに(第一〇二段)
- 四 五月ばかり、月もなういと暗きに(第一三一段)
- 五 村上の前帝の御時に(第一七五段)
- 六 雪のいと高う降りたるを(第二八〇段)
- 七 この草子
-
●付録
- 一 動詞活用表
- 二 形容詞・形容動詞活用表
- 三 古語敬語動詞
- 四 古語助動詞活用表
- 五 古語助詞一覧表
- 六 五十音図、月の異名、時刻・方位・十二支
- 七 内裏略図、清涼殿略図
- 八 日本古典文学関係年表
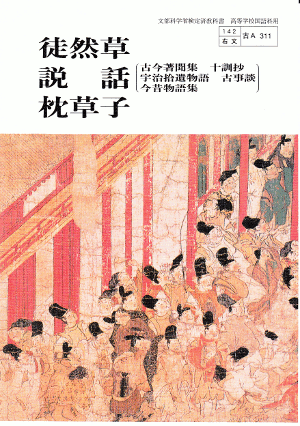 A5判・128ページ 2単位
A5判・128ページ 2単位